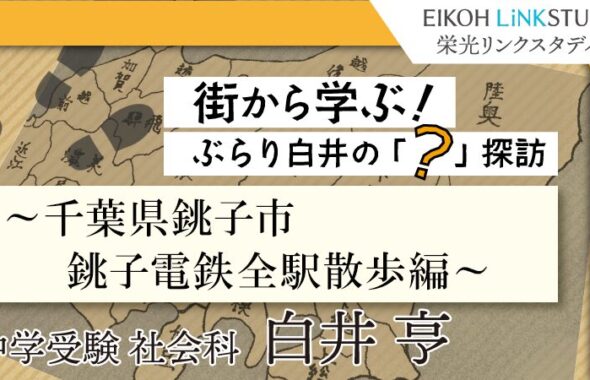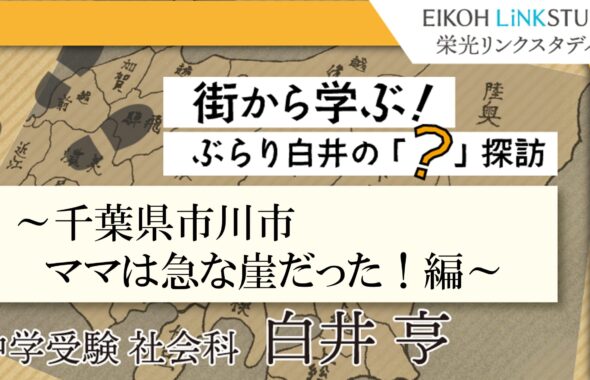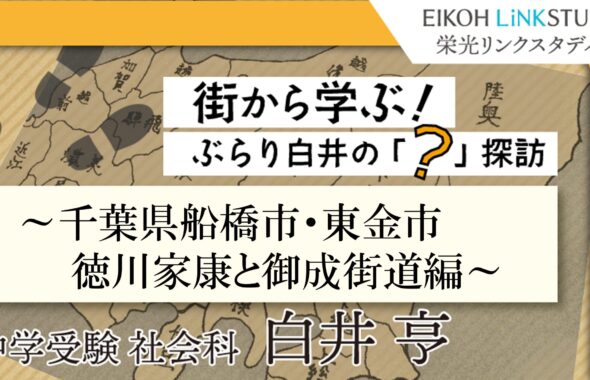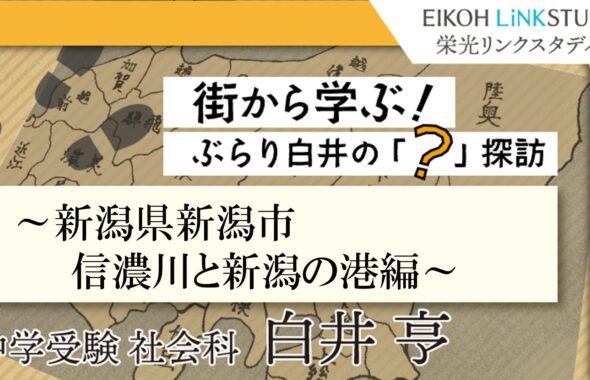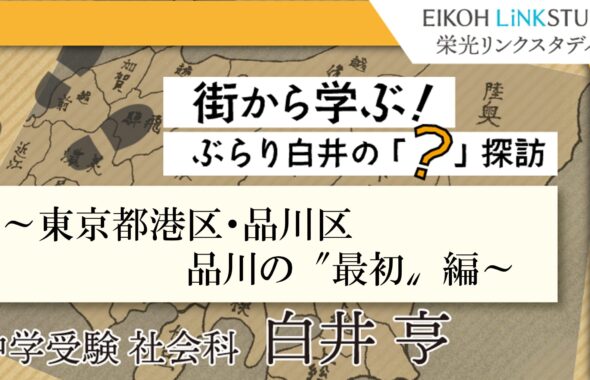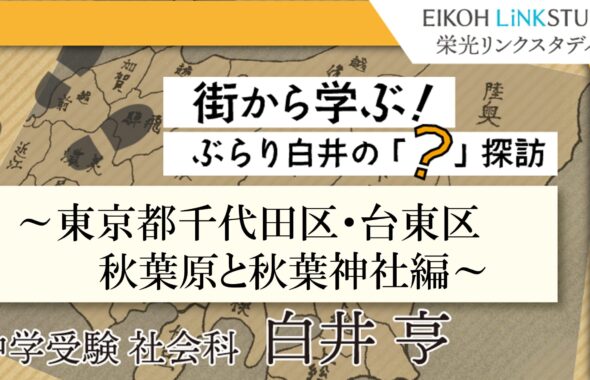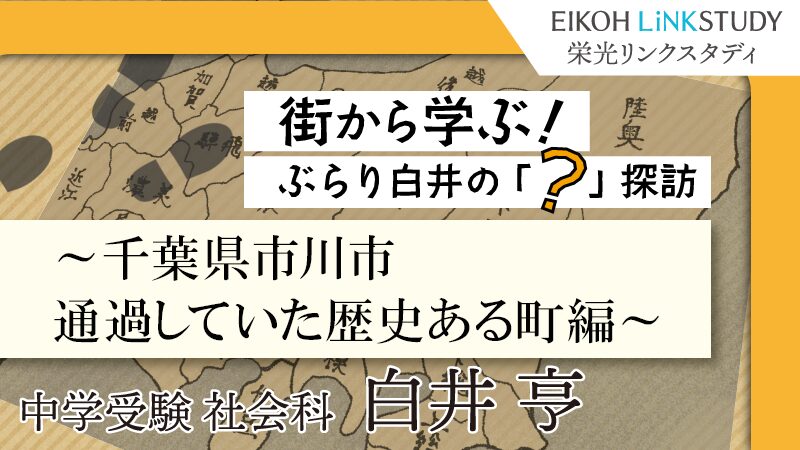
~千葉県市川市
通過していた歴史ある町編~
みなさんこんにちは。
リンスタ社会科担当の白井です。
西船橋駅から東京メトロ東西線に乗って2つ目の駅が妙典駅、その次が行徳駅です。この2つの駅名、なんとなく仏教の匂いを感じる名前だなぁ…と、以前から気になっていました。
調べてみたところ、妙典は鎌倉時代の僧日蓮が唱えた「南無妙法蓮華経」に由来するそうです。日蓮宗では法華経という経典を大切にしています。法華経というのは妙法蓮華経の略なのだそうです。また、行徳は戦国時代にこの地の発展に努めた金海法印という山伏のことを、徳が高く行いが正しいということから行徳さまと呼んだことが由来となっているのだとか。やはり、どちらの地名も予想通り仏教に関連していたのですね。
これまで幾度となく通過していた両駅ですが、ゆっくりと訪れてみたことはありませんでした。そこで今回はこのあたりを散策してみようと思い立ち、まずは地図を見てみることにしました。

東西線と旧江戸川に挟まれた地域に寺院の地図記号(卍)が数多く見られます。南西から北東にかけて、まるで道に沿うような感じで寺院が連なっているのは何か理由がありそうですね。寺院の多くあるところには「本行徳」という住所も見られ、おそらくこのあたりが元々の行徳だったのでしょうね。地名も仏教由来、寺院の数も多いということは、この町にはかつての繁栄の歴史があるはずですね。

まずは妙典駅で降りて、寺院の地図記号が多く見られるところに向かってみることにしました。
駅の東口を出て北西に向かう道を行くと、「寺町通り」書かれた道があったのでそちらを進んでいきます。一方通行の細い道なのですが、比較的広い歩道が整備されたとても歩きやすい道です。しばらく進んだところで見つけたのが下の写真の案内です。権現と言えば「東照大権現」として日光東照宮に祀られている徳川家康のことですね。どうやらこの道は、家康が東金に鷹狩りに行くときに通った道のようです。家康の鷹狩りのことは以前のブログ(千葉県船橋市・東金市 徳川家康と御成街道編)にも書きましたので、そちらをご覧ください。

権現道は、今は住宅地の中の細い道です。ただ、道沿いにはいくつかの寺院があり、それが由緒ある道らしさを感じさせてくれます。でも、なぜ家康はこの地を通っていたのでしょう?
実は、家康と行徳には深い関わりがあるということは以前のブログ(東京都江戸川区 船のエレベーター編)にも書いています。もう1年以上前のものなので、もう一度簡単に説明しますね。
1590年、江戸城に移った家康は、江戸に塩を安定的に供給できるようにするため、塩づくりがさかんだったこの地を直轄領とします。行徳でできた塩を江戸に輸送するために、江戸と行徳を結ぶ運河を開削させました。これが現在の小名木川です。家康は小名木川を船で進んで行徳に上陸し、御成街道を経て東金に向かったのですね。
その後、江戸と行徳の間には定期航路が開通します。すると、成田山新勝寺に向かう参拝客がこの航路を利用するようになり、成田街道につながる行徳街道が整備されます。妙典駅の東にある江戸川は、1919年につくられた放水路なので、江戸時代は川を渡ることなく成田方面に向かうことができたのです。
では、今度はその行徳街道を歩いてみることにします。
この道にはバスも通っているのですが、残念なことに歩道が整備されておらず、あまり快適に歩くことはできません。しかし、しばらく進んでいくと古い家屋が目につくようになりました。そのうちのいくつかを紹介していきますね。 まず気になったのは下の写真の加藤家住宅で、かつてこの地域の有力な塩問屋だったこの建物は登録有形文化財になっているそうです。和風の住宅とレンガ塀という組み合わせもおもしろいですよね。住宅とともにこのレンガ塀も登録有形文化財になっているようです。

次に気になったのが「笹屋うどん跡」という碑の建てられた下の写真の建物です。ここにあったうどん屋は「この地に来たら立ち寄らない人はいない」と言われたほどの大人気店だったそうです。江戸時代には『東海道中膝栗毛』の作者十返舎一九も立ち寄ったとか…。
また、笹屋という店名の由来は源頼朝にゆかりがあるとのこと。石橋山の合戦で敗れて空腹の頼朝一行をもてなしたのがここの主人で、頼朝が「源氏の家紋である〝笹りんどう〟をこの家のしるしにするがよい。これから笹屋と名乗ることにせよ」と言ったのだそうです。この話はちょっとあやしい気もしますけどね…(笑)

江戸時代の行徳は、物資輸送の拠点としても栄えていました。小名木川を使った航路は、塩だけでなく農産物や水産物を江戸に輸送するのにも使われたのです。江戸の日本橋近くには、行徳からの船が着くための河岸が設けられ、行徳河岸と呼ばれたそうです。かつての行徳は人や物資の輸送で賑わう港町だったということですね。また、「行徳千軒、寺百軒」という言葉があったように、寺町としての賑わいもあったようです。寺社の建立のため、腕の良い大工や仏師も多く住んでいました。明治時代になると寺社建立の数が減少し、そこで始められたのが神輿づくりでした。下の写真の建物は神輿づくりをしていた店のものなのですが、この店の方も元々は寺社の建立に関わった職人だったようです。

このような古い建築を楽しみながら行徳街道を歩いて行ったのですが、その繁栄の源となった港の痕跡がないのかということが気になってきました。地図を確認したところ、それらしきものが2つ見つかったので、まずは行徳河岸(祭札河岸)旧跡と書かれた場所に行ってみました。ここには説明版が建てられているだけでしたが、隣には小さな社があり、そこには湊水神宮と書かれた幟が立っていました。その名前から察するに、きっとこの小さな社は海や港で働く人たちの守り神だったのでしょうね。
そして、最後に訪れたのが、下の写真の常夜灯です。これは、成田へ参拝する人たちによって建てられたもので、航海の安全を祈願したものだそうです。常夜灯には「日本橋」の文字が刻まれていて、ここが江戸と繋がっていたことがわかります。江戸時代のこの場所は、たくさんの船が行き交い、多くの旅人や商人たちで賑わっていたのでしょうね。

東西線の快速電車は、妙典駅も行徳駅も通過してしまいます。東京方面に向かうときに東西線を利用していた私も快速電車に乗ることが多く、両駅ともほぼスルーしていたのです。そして、この付近に興味を持つこともなく、地図さえもほとんど見ていませんでした。旧江戸川が東西線とほぼ並行して流れていることも、今回地図を見て初めて気づいたくらいですからね。電車だけでなく、自分の目も完全にスルーしていたわけです。しかし、両駅の近くにはこんな魅力的なスポットがあったのですね。身近にありながら知らないことが、まだまだたくさんあるということを思い知らされた今回の散策でした。おそらく、数々の寺院にはそれぞれに由来があるはずです。それを確かめながら、お寺巡りをしてみるのも楽しそうです。
「?」はきっとそこにある
「?」を知ればおもしろい!みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。